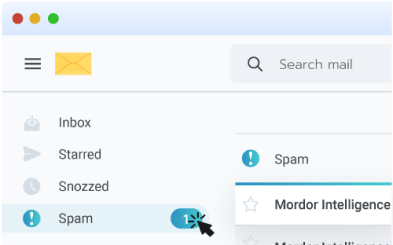マーケットトレンド の 海底ケーブルシステム 産業
市場の成長を牽引する乾燥植物製品
- ドライプラントは、ビーチのマンホールからケーブル陸揚げ局までの陸上の海底ケーブルネットワークセグメントで構成される。これには、給電装置(PFE)、海底線端末装置、ネットワーク管理システム、陸上ケーブルセグメントが含まれる。
- 世界の電気通信トラフィックは、ブロードバンド・サービスやネットワーク性能の向上に対する顧客の要求に応えて急速に拡大している。例えば、ITUによると、2023年までにアジア太平洋地域の固定ブロードバンド契約数は約8億4,800万件で、2022年と比較して約5,000万件の伸びを示している。その結果、海底通信システムの需要は、新しいケーブル・システムの建設だけでなく、既存のケーブル・システムの容量増強のためにも着実に増加している。この需要増に対応するため、複数の企業が光技術を活用した海底線端末装置(SLTE)の開発を進めている。
- 例えば、2023年10月には、グーグル・エキアーノケーブルのセントヘレナ支線が開通し、同島が高速海底光ファイバーケーブルを通じてインターネットに接続されるようになった。2023年6月までに、ケーブルの海底線端末装置の設置と統合が完了し、現地の地上光ファイバー・ネットワークの工事が開始された。
- 陸上ケーブルセグメントは、海底線端末とケーブル陸揚げ局の給電設備やその他のシステムをつなぐ。ネットワーク管理システムは、海底ケーブルシステム内のすべての機器を管理する統一プラットフォームとして機能し、ウェットプラント、給電装置(PFE)、オープンケーブルアクセス装置(OCAE)、および定期保守・運用中のネットワーク運用を監督します。
- ドライプラント製品は通常、強風、塩水噴霧、極端な温度などの過酷な沿岸環境条件に耐えるように設計されています。ドライプラントに障害が発生すると、海底ケーブルシステム全体のサービス停止につながるため、その設計は高い信頼性を優先しています。
トランス・パシフィックが大きなシェアを占める
- 太平洋横断地域では、1960年代に最初の太平洋横断海底ケーブル・システム(TPC-1(Trans-Pacific Cable 1))が運用された。これは海底同軸ケーブルで、日本、グアム、ハワイ、そしてハワイを経由してアメリカ本土を結ぶ、128回線という小規模なものだった。それ以来、数多くの太平洋横断海底ケーブル・システムが継続的に建設され、この地域の容量を大幅に拡大してきた。
- 海底ケーブルは、世界のインターネット・トラフィックの97%以上を処理しており、日常業務におけるインターネットへの依存度の高さを反映している。人々をグローバルにつなぐインターネットの能力は、国際トラフィックの継続的な増加につながっている。アジア太平洋地域は、世界のインターネット・トラフィックの約半分を占めており、海底通信ケーブルの需要を牽引している。同地域の一部の国では海底通信ケーブルが整備されていないため、太平洋横断地域でより高速なインターネット・サービスの必要性に拍車がかかり、世界銀行やアジア開発銀行のような組織が新たなケーブル・システムに資金を提供するようになった。
- 2022年7月、日本NTT、三井物産、PC Landing Corp.2022年7月、日本電信電話株式会社、三井物産株式会社、株式会社ピーシー・ランディング、JA三井リース株式会社は、新会社「セレン・ジュノ・ネットワーク株式会社(以下「セレン)の設立を発表した。(Seren), established to construct and operate JUNO, the most extensive trans-Pacific submarine cable system linking Japan and the United States.
- さらに2022年8月、日本電気株式会社は、セーレン・ジュノ・ネットワークが、米国カリフォルニア州と日本の千葉県および三重県を結ぶ太平洋横断光海底ケーブル「JUNOケーブルシステムの建設事業者に選定されたことを明らかにした。全長10,000kmを超えるこのケーブルは、2024年までに完成する予定である。
- 日本やオーストラリアをはじめとするこの地域の主要国は、海底ケーブルシステムを自国の経済成長に不可欠なものと考えており、海底ケーブル・ネットワークへの投資を強化している。例えば、日本政府は2023年7月、日本と世界を結ぶ海底ケーブルネットワークを拡大するため、デジタルインフラ開発基金を増強する計画を発表した。