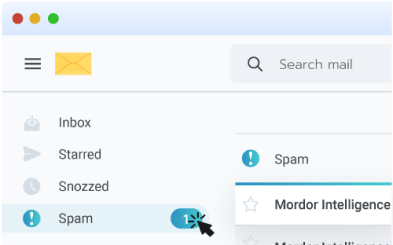の市場トレンド フィリピンの種籾市場
フィリピンは、主食需要を満たすためにコメ栽培に注力しており、小規模農家にとって種子の価格が安いため、OPVが主流となっている。
- フィリピンはアジア太平洋地域の主要な米生産国のひとつで、総面積の3.4%を占めている。米は人口の80%にとって重要な主食であり、多くの農家にとって豊かな収入源である。フィリピンでは、2022年の米生産面積は480万ヘクタールだった。米の栽培面積では第8位の国である。2016年から2022年にかけて栽培面積が6.2%増加したのは、生活水準の向上に伴い、高品質米への需要が高まっているためである。フィリピンの主な稲作地域は、ルソン島、西ビサヤ諸島、南部ミンダナオ島、中部ミンダナオ島である。米の収穫面積の60%近くは灌漑によるもので、残りのほとんどは低地での天水栽培である。全国の米生産面積の40%以上がルソン島である。
- ルソン島では、2022年の米生産面積のうち、ハイブリッド米の栽培面積は584.2千ヘクタールで、OPVが86.7%を占め、開放受粉品種やハイブリッド派生品種の栽培面積を下回っている。この高い作付面積シェアは、同国では小規模農家や零細農家がほとんどであるため、低コストの種子によるものである。しかし、ハイブリッド米の作付面積はOPVよりも急速に増加しており、生産性を高める可能性がある。
- 自給率に対する懸念の高まり、コメは全国で消費される主要な主食であるためコメ在庫の増加、市販種子の入手可能性の増加、遺伝子組み換えコメの採用、コメ耕作面積の増加が、予測期間中の同国のコメ種子市場を牽引すると予想される。
パートナーシップによる高収量生産に役立つ、高度な耐病性と幅広い適応性を持つ米種子への需要の高まりが、市場の成長を促進している。
- フィリピンでは、米は最も栽培されている主食作物である。生産される作物から高い収量と栄養価が要求され、土壌条件が変化するため、稲作において最も採用されている形質は適応性の広さである。例えば、Syngenta AGのS6003やS9001 Kharif、SL-20Hのような種子品種は、様々な条件下で早熟により高い収量を提供する。さらに、種子会社は、細菌病、褐色植物ホッパー、いもち病、登熟期の熱に対する抵抗性という他の主要な形質を提供するのが一般的である。主な種子会社には、Bayer AG、DCM Shriram Ltd (Bioseed)、Corteva Agriscience、SeedWorks International Pvt.Ltdなどがあり、細菌病やいもち病などの一般的な病気に耐性のある種子を提供している。
- フィリピンでは気象条件が変化しており、生産者が良質のコメを大量に生産できるよう、フィリピン稲研究所(PhilRice)と国際稲研究所(IRRI)は、干ばつに強く、水ストレス条件下でも生き延びることができるコメ品種を提供している。 さらに、2021年には、DCMシュリラムの子会社であるバイオシードが、IRRI(国際稲研究所)とパートナーシップ契約を締結し、フィリピン向けに干ばつや洪水条件に強いコメ品種を開発している。したがって、生産者の高い需要を満たすために、予測期間中に干ばつに強い種子品種の開発が増加すると予想される。
- 耐病性品種や耐干ばつ性品種などの新品種の増加は、米種子の需要を満たすために開発されている。これらは予測期間中の市場の成長に貢献すると期待される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 伝統的な品種改良は、自家受粉作物であるイネにおいて最も一般的な技術である。