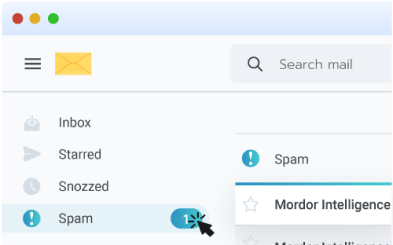マーケットトレンド の ジャパン・パワー 産業
火力発電が市場を支配する見込み
- 2023年時点で、日本の火力発電所は日本の総設備容量の46.96%近くを占め、日本のパワーミックスに最も貢献している。送電事業者地域間調整機構(OCCTO)によると、2023年時点の日本の火力発電設備容量は1506万kWで、481以上の発電所から供給されている。
- 経済産業省のデータによると、日本には火力発電資産を保有する発電事業者が214社近くある。しかし、日本の火力発電市場は旧一般電気事業者に支配されており、火力発電設備容量の合計が3GWを超える会社は、北海道電力、東北電力、JERA、北陸電力、関西電力などの大手企業を含めても10社にすぎない。
- 日本の火力発電部門はLNG火力発電所によって占められており、総発電容量の53.1%近くを占めている。経済産業省の統計によると、日本には69の発電所があり、平均設備容量は110万kWである。次いで石炭火力発電所が95基近くあり、総設備容量の32.2%を占めている。
- しかし、ロシアとウクライナの紛争が始まって以来、日本のLNG供給状況はますます悪化している。例えば、2023年には600万トン/年(MTPA)近くのLNG長期供給契約が期限切れとなり、日本の契約上のLNG供給量は8%近く減少すると予想されていた。
- この傾向を逆転させるため、日本企業は2022年に主要LNG供給国と新たな契約を交渉した。例えば、2022年12月、日本企業は燃料供給を確保し将来の供給不足を回避するため、米国およびオマーンと大規模な長期LNG調達契約を締結した。2022年12月、日本の発電事業者であるJERA、商社の三井物産と伊藤忠商事は、供給元のオマーンLNGと、2025年から10年間で合計約2MTPAのLNGをオマーンから輸入する基本契約を締結した。
- したがって、上記の要因により、予測期間中、火力発電が電力市場の最大セグメントとなる見込みである。
再生可能エネルギー技術の進歩と政府の支援策
- 日本の再生可能エネルギー発電部門は、よりクリーンなエネルギー源への移行に向けた政府の強力なイニシアチ ブと、再生可能エネルギー技術の継続的な進歩に牽引され、大きな成長を遂げようとしている。日本は野心的な気候変動目標を設定し、カーボンニュートラルを目指している。
- 2021年10月、日本は第6次エネルギー戦略計画を発表し、エネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を2030年までに36%から38%に引き上げるという目標を概説した。脱原発に伴い、日本は太陽光発電、風力発電、潮力発電などの自然エネルギーの導入を加速させており、外国エネルギーへの依存を減らし、国内のエネルギー・イノベーションを促進することを目指している。
- 2020年10月、日本の経済産業省は2050年までにカーボンニュートラルを目指す「グリーン成長戦略を発表した。この戦略では、自然エネルギーの野心的な推進、原子力の復活、低炭素水素、先進原子炉、カーボン・リサイクルなどの最先端技術の導入が概説された。2021年には同戦略が改定され、エネルギーやその他の分野の研究・技術革新への多額の投資が強調され、企業の研究開発政策に影響を与える可能性がある。こうした動きは、再生可能技術の進歩を促進する態勢を整えている。
- 2021年4月、富士通株式会社とオートグリッド・システムズ社は、富士通がオートグリッド社のバーチャルパワープラント(VPP)ソリューションを日本市場に導入する計画を発表した。この動きは、分散型エネルギー資源の利用を最適化し、再生可能エネルギーの導入を促進し、脱炭素化への取り組みを加速することを目的としている。
- 2022年、日本の太陽光発電による発電量は約93TWh、水力発電による発電量は77TWhを超えた。温室効果ガスの排出量を削減し、化石燃料の輸入依存度を下げるため、日本政府は現在、再生可能エネルギーによる電力生産の拡大に取り組んでいる。
- 今回の合意の一環として、富士通はオートグリッド社の主力VPPソリューションであるオートグリッドフレックスTMを日本で販売する。これらのシステムは、監視・制御機能を強化し、発電オペレーションを最適化する。日本は、費用対効果の高い低炭素電力生産技術を積極的に求めており、自然エネルギーの進歩は、今後数年間の日本のエネルギー事情にとって極めて重要である。
- 政策、制度、野心的な再生可能エネルギー目標など、こうした政府の強力な後押しを受け、日本の再生可能エネル ギー市場は今後数年間で成長する態勢を整えている。