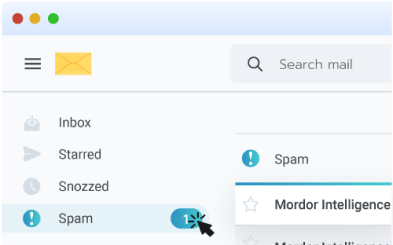マーケットトレンド の 日本の集積回路(IC)市場 産業
ロジックに次いで大きなシェアを獲得するメモリ部門
- 現在DRAMは、低コストで大容量のメモリが必要とされるデジタル電子機器に広く使われている。DRAMの最大の用途のひとつは、最新のコンピュータやグラフィックカードのメインメモリである。また、多くの携帯機器やビデオゲーム機でも一般的に使用されている。
- 日本の5G展開はまだ初期段階にあるが、2021年の開始以来、日本の携帯電話会社は5G展開を加速させている。例えば、ソフトバンクは2022年3月末までに5万以上の5G基地局を配備し、人口カバー率90%を目指す。同様に、NTTドコモも2024年3月までに日本の人口の90%をカバーすることを目指している。
- 5Gの実装に伴い、モバイル機器は5G対応のマルチメディア・アプリケーションやタスクを処理するため、LPDDR5などのより高速なDRAMを必要とするようになる。また、5Gに伴うダウンロード速度と容量の増加により、より高速で大容量のストレージの必要性が高まる。
- NANDフラッシュ・チップは、電源を切るとデータが失われるDRAMチップとは異なり、デバイスの電源を切ってもデータを保持します。NANDフラッシュ・メモリは、フラッシュ・ストレージ・デバイスと呼ばれるソリッド・ステート・ドライブ(SSD)やUSBフラッシュ・ドライブとして使用されるため、人気が高まっている。また、在宅ワークの流行により、パソコンやスマートフォンの需要に伴い、NANDフラッシュの消費量が飛躍的に増加している。
- さらに、2022年7月、マイクロン・テクノロジーは、コンシューマー・ガジェット、自動車、データセンターからの激しいデータ利用に対応できる232層のメモリセルからなる最先端のNANDフラッシュ・チップの出荷を開始したと発表した。
産業用アプリケーションは大きな成長率
- インダストリー4.0は、企業が製品を製造する方法を変革している。インダストリー4.0とは、リアルタイムで生産をサポートする意思決定を行うために、物理的な世界を感知、予測、または相互作用するように設計されたスマートでコネクテッドな生産システムを指す。インダストリー4.0は、製造業の生産性、エネルギー効率、持続可能性を向上させる可能性がある。
- JARAによると、2023年の日本のマニピュレーターとロボットの生産額は約8,915億6,000万円(55億1,000万米ドル)で、前年比12.7%減少した。この期間の日本の生産台数は約2205.8万台であった。
- 集積回路は、ロボットやそのコントローラーに幅広く使用されている。例えば、メモリー・コンポーネントは、あらゆる産業用ロボットの中核要素を形成している。メモリー・チップは、さまざまな産業向けのロボット・ソリューションに組み込まれたコントローラーやセンサーの機能、データ・ロギングにおいて重要な役割を果たしている。
- さらに、アナログICやミックスドシグナルICは、産業オートメーションやプロセス制御アプリケーションで重要な役割を果たしている。産業用システム開発者のニーズの高まりを受けて、ここ数年、アナログICベンダーは、工場用ロボット、機械の状態監視用センサー、高度なモーターシステムなど、さまざまな産業用設計ニーズに対応するよう設計された新しいチップを展開し続けている。
- また、日本ではスマート工場の推進を目的としたコネクテッド・インダストリーズ戦略が開始された。その結果、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)が創設され、データ連携・活用による生産性向上に必要なシステム、センサー、ロボットなどの導入に対する財政支援が行われるようになり、これも国内の同分野の市場需要を後押ししている。