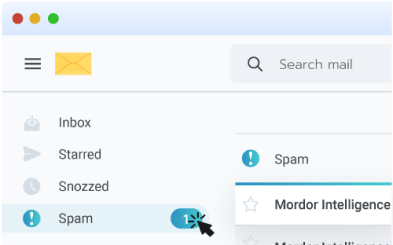マーケットトレンド の 建物一体型太陽光発電 (BIPV) 産業
住宅部門は大幅な市場成長が期待される
- 住宅建設が急増するにつれ、建物一体型太陽光発電(BIPV)の統合も進んでいる。新しい住宅が建つたびに、屋根、ファサード、窓にソーラー技術を組み込む機会が生まれている。この傾向は、持続可能性に関する規制、エネルギー効率の向上、ソーラー技術のコスト低下によってさらに加速している。
- 世界的に、都市化、人口増加、中間層の急増を背景に、住宅需要は増加の一途をたどっている。こうした要因が住宅供給を上回り、価格を押し上げ、値ごろ感という課題を生み出している。
- 住宅は米国経済において極めて重要な役割を担っており、新築、中古住宅販売、住宅改修を含み、これらすべてがGDPを押し上げている。米国国勢調査局のデータでは、2019年から2024年にかけて、米国の公共住宅建設支出が大幅に増加することが明らかになっている。住宅プロジェクトに対する公共部門の支出は、2019年の約68億9,000万米ドルから、2024年には117億米ドルという驚異的な規模に跳ね上がった。新規住宅建設額の継続的な増加が予測されており、こうした傾向はBIPV市場にとって好材料となる。
- さらに、企業はPV技術を住宅に積極的に組み込もうとしている。注目すべき例がある:2025年2月、カナダの企業が半透明および不透明な太陽光発電用手すりシステムを発売した。
- 世界的なエネルギー危機と電力セクターの脱炭素化が推進される中、分散型発電が注目を集めている。その結果、住宅部門は今後数年間、BIPV技術の展開を主導する態勢を整えている。
アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
- アジア太平洋地域は、さまざまな産業で太陽光発電技術を巧みに採用し、特筆すべき費用対効果を達成してきた。この地域の太陽光発電技術は成熟し、価格は一貫して下落している。
- 中国、インド、日本、ASEAN諸国は、BIPVや屋上設置のような革新的技術を開拓し、太陽光発電の実力を示してきた。特筆すべきは、中国の太陽光発電産業における生産量が世界規模の50%を超え、トップランナーとしての地位を確固たるものにしていることだ。
- BIPVは、クリーンエネルギーの利用、二酸化炭素排出の抑制、エネルギー効率の向上により持続可能性を擁護する建設部門で極めて重要な役割を担っている。グリーンビルディング認証が勢いを増すなか、PV一体型ビルは持続可能な開発の模範として台頭し、より環境に優しい未来へと舵を切ることになるだろう。
- 中国は、2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという気候目標を意欲的に掲げている。2021年10月に中国国務院によって導入された「2030年までの二酸化炭素排出量ピークアウトのための行動計画によると、建築物における再生可能エネルギーの推進が顕著で、ソーラーパネルとの統合が強調されている。
- 最新のエネルギー白書では、中国政府は省エネ建築基準を引き上げるというコミットメントを強調している。このビジョンを支持し、31以上の省がグリーンビル建設を支持する政策を展開している。
- 中国はまた、新しいBIPV製品の開発の最前線にいる。例えば、2025年2月、無錫にあるUtmoLightのギガワット規模のペロブスカイト太陽電池モジュールの生産施設が生産を開始し、超大型ペロブスカイトモジュールとBIPV製品に焦点を当て、年間180万枚のモジュールの生産が見込まれている。
- BIPV分野では日本も負けてはいない。2023年8月、パナソニックホールディングス株式会社は、建物一体型ペロブスカイト太陽電池ガラスのプロトタイプを発表し、神奈川県Fujisawaサステイナブル・スマートタウンのモデルハウス「未来共創ファインコートIIIで1年間の技術試験を開始した。
- 日本は、2030年の再生可能エネルギー公約と脱炭素化目標に向け、再生可能エネルギーの強化策を模索している。太陽光発電が土地開発の課題に直面するなか、BIPVは発電容量を拡大するための迅速なソリューションとして浮上している。日本の国や地方自治体は、家庭や企業へのBIPVシステム設置を促進する政策を展開している。
- このような動きを考えると、アジア太平洋地域は当面の間、市場をリードしていくものと思われる。