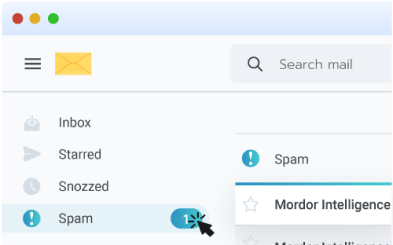マーケットトレンド の アジア太平洋浮体式洋上風力発電 産業
市場を牽引すると期待されるアジア諸国での今後のプロジェクト
- 多くのアジア諸国は、浮体式洋上風力発電技術を利用する潜在的な可能性を見出している。例えば、日本政府は最近、浮体式洋上風力発電のポテンシャルを約424GWと認定した。そのため、日本はその利用に向けて多くの計画を立てている。
- 日本の現在の風力発電容量は、2021年時点で8.2TWhである。日本はすでに、2030年までに約10GW、2040年までに30~45GWの洋上風力発電容量を導入するという野心的な計画を立てている。この目標は、浮体式洋上風力発電プロジェクトによっても達成されようとしている。
- 例えば、2022年5月、BW Ideolと東北電力は、岩手県久慈市沖で浮体式洋上風力発電所を共同開発することで合意した。このプロジェクトは現在、フィージビリティ・スタディの段階にある。
- さらに、韓国政府は2022年11月、約6GWの世界最大の浮体式洋上風力発電所を国内に建設する新たな計画を発表した。政府は、このプロジェクトへの投資計画を400億米ドルと公表した。プロジェクトは韓国南東部の工業都市、蔚山の沖合に建設される予定だ。
- このような動きは、今後数年間、アジア太平洋地域の浮体式洋上風力発電市場を牽引していくと予想される。
著しい成長が期待される中国
- 中国は、2021年には世界レベルで洋上風力発電の設置容量におけるリーダーになると位置づけられている。2021年の稼働洋上風力発電容量は27GWを記録した。固定式洋上風力発電でこれほど目覚ましい成長を遂げたのであれば、浮体式洋上風力発電も見逃せない。
- 同国の風力発電のシェアは約655.6TWhで、再生可能エネルギーの中で最も高い。中国政府は、浮体式洋上風力発電の設置とともに、このシェアを拡大するために多くの計画を立てている。中国は現在、約5.5MWの浮体式洋上風力発電設備容量で第5位に位置しており、2026年までに約477MWの設備容量を目標としている。このように、多くの新しい発電所がポートフォリオに追加されようとしている。
- その一例として、中国広東省の華南海域北部の水深400フィート(約1.5メートル)に設置されるCNOOCの深海浮体式洋上風力発電プロジェクトが待ち望まれている。この発電所は現在開発段階にあり、2023年までに稼働する予定だ。
- さらに2021年12月には、別の浮体式洋上ウィンドファーム・プロジェクトが稼働を開始した。容量5.5メガワットの洋上風力発電プロジェクトは、三峡銀嶺昊(Sanxia Yinling Hao)と呼ばれる浮体式風力タービンを搭載し、稼働に成功した。このプロジェクトは中国三峡風力発電とMingyang Smart Energyによって開発された。
- このような開発により、中国がアジア太平洋の浮体式洋上風力発電市場のトップランナーになると予測されている。